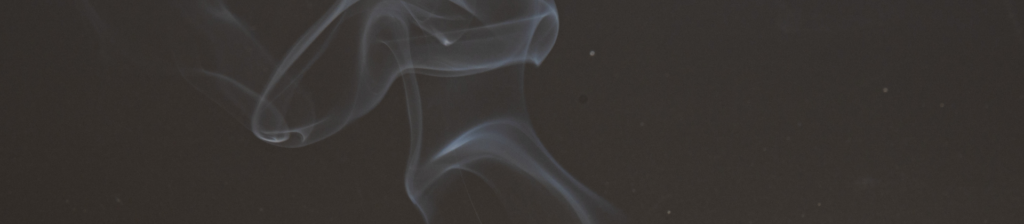
プルースト全集1
失われた時を求めて 第一篇スワン家のほうへ
原作:プルースト 翻訳:井上究一郎 1984年初版 筑摩書房
56-61ページ プルースト効果の記述部分
私はケルト人の信仰をいかにももっともだと思う、それによると、われわれが亡くした人々の魂は、何か下等物、獣とか植物とか無生物とかのなかに囚われていて、われわれがその木のそばを通りかかったり、そうした魂がとじこめられている物を手に入れたりする日、けっして多くの人々には到来することのないそのような日にめぐりあうまでは、われわれにとってはなるほど失われたものである。
ところがそんな日がくると、亡くなった人々の魂はふるえ、われわれを呼ぶ、そしてわれわれがその声をききわけると、たちまち呪縛は解かれる。われわれによって解放された魂は、死にうちかったのであって、ふたたび帰ってきてわれわれとともに生きるのである。
われわれの過去もまたそのようなものである。過去を喚起しようとつとめるのは空しい労力であり、われわれの理知のあらゆる努力はむだである。過去は理知の領域のそと、その力のおよばないところで、何か思いがけない物質のなかに (そんな物質があたえてくれるであろう感覚のなかに)かくされている。その物質に、われわれが死ぬよりまえに出会うか、または出会わないかは、偶然によるのである。
私の就寝の舞台とドラマ、私にとってそれ以外のものが、コンプレーから、何一つ存在しなくなって以来、すでに多くの年月を経ていたが、そんなある冬の日、私が家に帰ってくると、母が、私のさむそうなのを見て、いつもの私の習慣に反して、すこし紅茶を飲ませてもらうようにと言いだした。はじめはことわった、
それから、なぜか私は思いなおした。彼女はお菓子をとりにやったが、それは帆立貝のほそいみぞのついた貝殻の型に入れられたように見える、あの小づくりでまるくふとった、カチット・マドレーヌと呼ばれるお菓子の一つだった。そしてまもなく私は、うっとうしかった一日とあする陰気な日であろうという見通しとにうちひしがれて、機械的に、一さじの紅茶、私がマドレーヌの一きれをやわらかく溶かしておいた紅茶を、唇にもっていった。
しかし、お菓子のかけらのまじった一口の紅茶が、口蓋にふれた瞬間に、私は身ぶるいした、私のなかに起こっている異常なことに気がついて。 すばらしい快感が私を襲ったのであった、孤立した、原因のわからない快感である。その快感は、たちまち私に人生の転を無縁のものにし、人生の災厄を無害だと思わせ、 人生の短さを錯覚だと感じさせたのであった、あたかも恋のはたらきとおなじように、そして何か貴重な本質で私を満たしながら、というよりも、その本質は私のなかにあるのではなくて、私そのものであった。
私は自分をつまらないもの、偶発的なもの、死すべきものと感じることをすでにやめていた。一体どこから私にやってくることができたのか、この力強いよろこびは? それは紅茶とお菓子との味につながっている、しかしそんな味を無限に越えている、したがっておなじ性質のものであるはずはない、と私は感じるのであった。このよろこびはどこからきていたのか? それは何を意味していたのか? どこでそれを把握するのか?
私は二口目を飲む、そこには一口目のとき以上のものは何も私に見出されない、三口目は二口目よりもすこし劣ったものしか私にもたらさない。もう私はやめるべきだ。 飲物の効力は減ってゆくようだ。あきらかに、私が求める真実は、飲物のなかにはなくて、私のなかにある。飲物は私のなかに真実を呼びおこしたが、その真実が何であるかを知らず、次第に力を失いながら、漫然とおなじ証言をくりかえすにすぎないし、私もまたその証言を解釈するすべを知らないで、せめてその証言をもう一度飲物に求めることができたらと思い、またその証言をそっくりそのままもう一度見出して、いつかの決定的な解明に役立つように、いますぐその証言を自分の自由にしておくことができたらと思うのだ。
私は茶碗を置き、私の精神をふりかえる。 真実を見出すことこそ精神-精神がそれ自身の能力を越えた領域にふみこんだのつとめだ。しかし、どのようにして? 深刻な不安、と感じるときの、そして探究者自体である精神が、すっかり真暗な世界となって、そんななかで探究しなくてはならなかったり、手持の全知識が何一つ役立たなかったりするときの、深刻な不安。探究する? それだけではない、創造するのだ。 精神は、まだ存在していない何物かに直面しているのだ、精神だけがそれを現実に存在させ、やがてそれを自分の光のなかにはいらせることができるのだ。
それから私はふたたび自分にたずねはじめる、 一体あの未知の状態は何であったか、どんな論理的な証拠をもたらすこともなかったが、それがもたらした幸福感の明白性、実在感の明白性が、他のすべての状態を消しさっていた、あの未知の状態は何であったか、と。私はそんな状態をもう一度出現させることを試みようとする。思考の流をさかのぼって、紅茶の最初の一さじを飲んだ瞬間に私はもどる。ふたたび同一の状態を見出すが、新しい光明はない。もう一段の努力を、逃げさる感覚をもう一度連れもどすことを、私は精神に要求する。
そして、私の精神がその感覚をふたたびとらえようとして試みる飛躍にたいするあらゆる障害をしりぞけ、飛躍とは無縁のあらゆる観念をしりぞけて、その飛躍が何に会ってもくじけないようにするために、私は隣室の物音に耳をふさぎ、注意をそらさないようにする。しかし、精神が疲れるばかりでうまく行かないのを私は感じ、こんどは反対に、いままで精神に禁じていたあの息ぬきをとること、思考をそらすこと、最後の試をまえにして元気をとりもどすことを精神に強いる。ついで、再度私は精神のまえに空白をつくる、あらためて私は精神をあの最初の一口のまだ新しい味に対面させる、すると、私の内部で何かが身ぶるいするのを私は感じる、それは沈んでいる場所から動き、上にあがってこようとする何かであり、非常に深いところで、錨のようにひきあげられようとした何かだ。私はそれが何であるかは知らない、しかしそれはゆっくりとあがってくる、私はそれの抵抗を感じ、それが経由してくる距離の鈍いひびきを耳にする。
なるほど、そのように私の底でぴくぴくしているもの、それはあの味にむすびつき、あの味のあとについて私の表面まであがってこようとする映像、視覚的回想にちがいない、しかしそれはあまりにも遠くで、またあまりにも見さだめにくい形で、動いているのであって、かきまぜられたさまざまな色彩のとらえにくい渦巻が溶けこんだその鈍い反映はどうにかそれと私に認められても、その形は判別できないし、可能な唯一の通訳のあの味 の証ように、その反映にたいして、それと同時に生まれそれと切りはなすことができない伴侶-あの味-の証言を、翻訳してくれるようにたのむことも、それがどんな特殊な事情、どんな過去の時期に関しているかを教えてくれるようにたのむことも、私にはできないのだ。
この回想、この古い昔の瞬間は、私の明瞭な意識の表面にまで達するだろうか、昔と同一のある瞬間の吸引力が非常に遠くから作用して、いま私の奥底で、この昔の瞬間をうながし、はげまし、ふるいたたせようとしたこのときに? 私は知らない。もう私は何も感じない、回想は停止し、ふたたび沈んでしまったらしい、誰が知ろう、それがいつかまたその暗夜からあがってくることを? 十回も私はやりなおし、その回想のほうにかがみこまなくてはならない。そして、そのたびに、困難なつとめ、重大な仕事といえば何にでもわれわれを尻ごみさせるあの卑怯さが、そんなものは投げだすのだ、苦もなく反芻されるきょうの私の倦怠、あすの私の欲望を考えるだけにして、いつもの紅茶を飲んでいればいい、と私に忠告した。
突如として、そのとき回想が私にあらわれた。この味覚、それはマドレーヌの小さなかけらの味覚だった、コンプレーで、日曜日の朝(というのは、日曜日はミサの時間になるまで私は外出しなかったから)、私がレオニー叔母の部屋におはようを言いに行くと、叔母は彼女がいつも飲んでいるお茶の葉またはぼだい樹の花を煎じたもののなかに、そのマドレーヌをひたしてから、それを私にすすめてくれるのであった。
プチット・マドレーヌは、それを眺めただけで味わってみなかったあいだは、何も私に思いださせなかった、というのも、おそらく、そののちしばしば菓子屋の棚でそれを見かけたが、たべることはなかったので、それの映像がコンブレーのあの日々と離れて、他のもっと新しい日々にむすびついてしまったからであろう、またおそらく、それほど長いあいだ記憶のそとにすてさられたそんなさまざまな回想からは、何一つ生きのこっているものはなかったし、すべては解体してしまったからであろう、それらの物の形態は 謹厳で信心深いその襞につつまれてあんなに豊満な肉感をもっていたお菓子のあの小さな貝殻の形もおなじように 消滅してしまったのだ、それとも、眠りこんで、ふたたび意識にむすびつくだけの膨張力を失ってしまったのだ。
しかし、古い過去から、人々が死に、さまざまな物が崩壊したあとに、存続するものが何もなくても、ただ何と味だけは、かよわくはあるが、もっと根強く、もっと形なく、もっと執拗に、もっと忠実に、魂のように、ずっと長いあいだ残っていて、他のすべてのものの廃墟の上に、思いうかべ、待ちうけ、希望し、匂と味のほとんど感知されないほどのわずかなしずくの上に、たわむことなくささえるのだ、回想の巨大な建築を。
そして私が、ぼだい樹花を煎じたものにひたして叔母が出してくれたマドレーヌのかけらの味覚だと気がついたとたんに(なぜその回想が私をそんなに幸福にしたかは、私にはまだわからず、その理由の発見をずいぶんのちまで見送らなくてはならなかったが)、たちまち、表通に面していてそこに叔母の部屋があった灰色の古い家が、芝居の舞台装置のようにあらわれて、それの背後に、庭に面して、私の両親のために建てられていた、小さな別棟につながった(私がこれまでに思いうかべたのはこの別棟の截断面だけであった)、そしてこの母屋とともに、朝から晩にいたるあらゆる天候のもとにおける町が、昼食までに私がよく送りだされた広場が、私がお使に行った通が、天気がいいときにみんなで足をのばした道筋が、あらわれた。
そしてあたかも、水を満たした陶器の鉢に小さな紙きれをひたして日本人がたのしむあそびで、それまで何かはっきりわからなかったその紙きれが、水につけられたとたんに、のび、まるくなり、色づき、わかれ、しっかりした、まぎれもない、花となり、家となり、人となるように、おなじくいま、私たちの庭のすべての花、そしてスワン氏の庭園のすべての花、そしてヴィヴォーヌ川の睡蓮、そして村の善良な人たちと彼らのささやかな住まい、そし教会、そして全コンプレーとその近郷、形態をそなえ堅牢性をもつそうしたすべてが、町も庭もともに、私の一杯の紅茶から出てきたのである。
